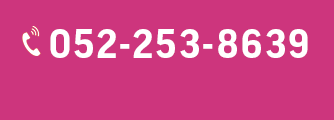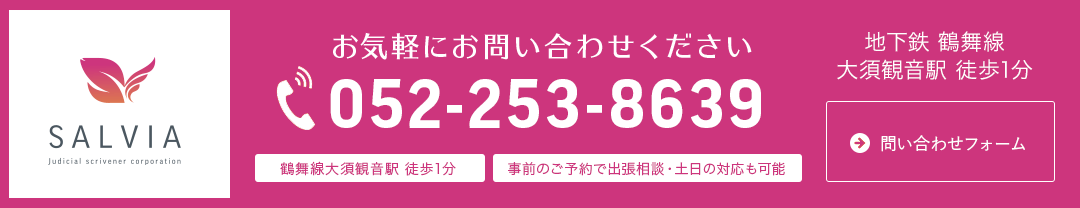遺言
遺言は残された遺族へのメッセージであるとともに、相続の手続きにおいて遺族の負担を軽減したり、争いを防止するための大切なものです。
なお、遺言は書式や記載事項が法律で細かく定められており、それを知らずに書いても法的に無効になってしまう恐れがありますので、必ず専門家にご相談のうえ作成するようにしましょう。
当事務所の遺言書作成サポートの特徴
残される遺族の相続に関する負担を軽減します。
残された遺族にとって、悲しみの中での相続手続きは非常に大きな負担になります。そのため、その負担を軽減するために、遺言内容にそって相続の手続きを行う遺言執行者に当事務所の司法書士が就任することも可能です。
場合によってはご存命のうちに当事務所と死後事務委任契約(葬儀や埋葬、お墓を手配する行う契約)を締結していただくことで、葬儀や埋葬、お墓の手配を遺族に代わって当事務所が行うこともできます。
過去の事例を基に起こりうるトラブルとその事前対策をお伝えします。
例えば、「この遺産の分け方だと、こういった理由で相続人同士が揉めてしまったケースがあります。」など、過去の実際の事例に基づき、起こりうるトラブルを事前にお伝えします。
もちろん、そういったリスクに対する対策についてもご提案をさせていただきます。
遺留分や寄与分、特別受益などまで考慮してアドバイスします。
特定の相続人にのみ相続を相続させたい場合などに問題になりやすいのが遺留分です。
遺留分とは相続人が最低限相続できる財産のことで、遺言書で特定の相続人にのみ相続させる旨を記載しても、他の相続人がこの遺留分を請求すると法律で定められた遺留分の割合をその相続人に配分しなくてはなりません。
当事務所ではそういった相続に関する法律的な問題まで考慮して、必要な対策をご提案いたします。
税理士と連携して相続税のことまで考慮して生前対策をご提案します。
例えば、特定の相続人に家などの不動産のみを相続させた場合、相続税が払えずに結局その不動産を売却しなくてはならないなどのトラブルが発生する可能性があります。
また、相続税が発生する可能性がある方には、税理士と連携して事前に相続税対策や、相続人の納税対策までご提案いたします。
万が一のときでも柔軟に対応できる遺言書を作ります。
例えば奥様のために遺言書を書いたとしても、万が一、先に奥様が亡くなってしまった場合はその遺言書が無効になってしまいます。
そこで、万が一に備えて「妻が自分よりも先に亡くなった場合は○○に相続させる」といった遺言内容にすることもできますので、そういったことも考慮してご相談者様のご要望をお伺いします。