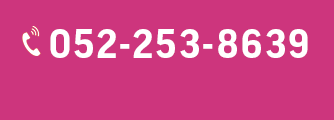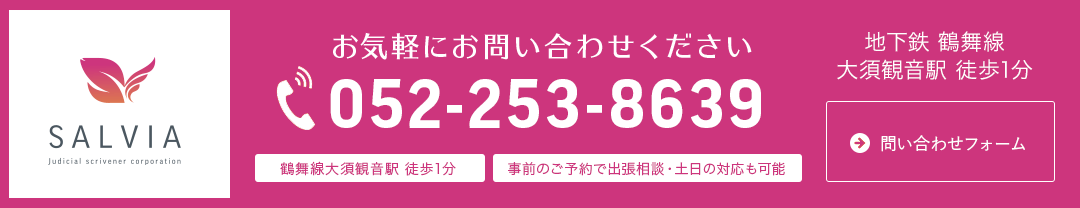成年後見Q&A
身寄りの親戚がいない場合でも、成年後見の申立はできますか?
民法で定められた申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族のいずれかですが、別の法律で市町村長による申立も認められるケースがあります。
市町村役場で相談をしてみると良いと思います。
成年後見制度を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか?
費用としては、①裁判所に納付する費用、②申立書の書類作成を行う司法書士の費用、③鑑定が必要な場合の鑑定費用の3種類の費用が必要です。具体的な内容は以下の通りです。
①裁判所に納付する費用・・・・申立にかかる収入印紙・切手代、後見登記にかかる収入印紙
②書類作成費用・・・・申立にかかる書類の作成報酬です。当事務所では10万円を頂いておりますが、詳しくはこちらをご覧ください。
③鑑定に要する費用・・・・本人の判断能力について医師による診断を裁判所が求める場合に必要となります。あくまでも、「裁判所が求める場合」に限られますので、必ずしも必要な費用ではありませんが、「後見」「補佐」については本人の権利を制限する制度なので、本人の判断能力について慎重に判断する必要があるため、原則的に鑑定を行います。
成年後見制度の申立てから開始までどれくらいの期間がかかりますか?
後見人候補者がいる場合
名古屋家庭裁判所の場合、まずは後見人候補者の方の面接を行う日程の予約を取り、その一週間前までに管轄裁判所に申立書を提出します。
候補者の面接と書類の審査が終了すると、成年後見開始審判がなされます。裁判所の処理状況や申立書に不備がある場合には時期が遅れることもありますが、目安として約1か月程度かかります。
後見人候補者がいない場合
申立書を提出した後に後見人を選定することになるため、候補者がいる場合に比べて時間を要します。ケースによって後見開始審判までに要する時間は区々ですので、余裕をもって申立を行いましょう。
なお、候補者がいない場合には、当事務所で候補者になれる専門家を予めご紹介することも可能ですので、候補者がいない場合も、お気軽にご相談ください。
成年後見制度を利用した場合、本人(被後見人)選挙権を失ってしまうのでしょうか?
平成25年7月以降に公示される選挙から、選挙権を行使できるようになりました。
詳しくは、総務省のHPをご覧ください。→http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/index.html
改正前は、公職選挙法の規定により、成年被後見人は選挙権・被選挙権を有しないものとされていましたが、改正後は、たとえ成年後見が開始した場合でも、本人は選挙権・被選挙権を失うことはありません。
成年後見が開始した後には、登記が必要ですか?
後見開始の審判がなされると、裁判所から法務局へ「嘱託」によって後見登記なされますので、ご自身で登記を行う必要はありません。
ただし、後見開始の審判後に後見人の住所や氏名・被後見人の住所や氏名等に変更が生じた場合には、別途変更登記をご自身で申請する必要があります。
後見登記事項証明書は、各法務局・地方法務局で取得することができますが、変更登記の申請は東京法務局に申請する必要があります。
申請方法についてもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。