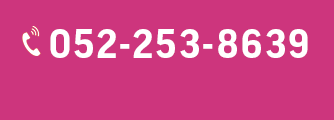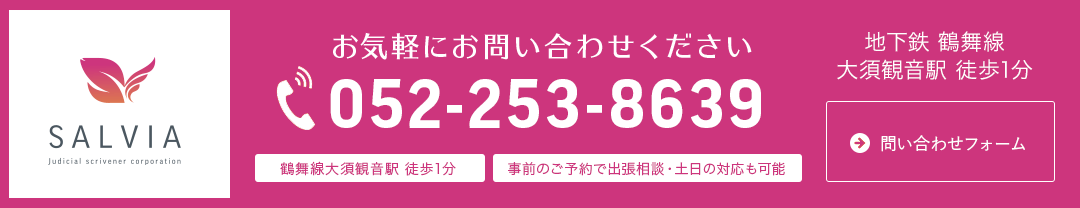成年後見人の選定と後見人の仕事
成年後見人になった人は、被後見人へのサポートに責任が発生します。
後見人は、被後見人の生活のさまざまなサポートを行います。
成年後見人の仕事を大きく分けますと、
1、選任直後になすべき事務
2、財産管理事務
3、身上監護事務
4、その他の事務 に分けられるといえます。
1、選任直後になすべき事務
(1)成年後見人選任直後になすべき事務として、今後の生活の計画を立案していく上で成年被後見人の状況の把握があります。
親族の成年後見人と異なり、司法書士や弁護士等の第三者後見人は、成年後見選任時に事情を把握していないため、家庭裁判所において記録を閲覧する、成年被後見人やその親族と面談する、親族以外のケアマネージャー等と面談することで状況を確認することが必要となります。
(2)成年後見人が成年被後見人の状況を確認したら、今後の財産管理を行うため、成年被後見人の財産等について占有を確保しなければなりません。
その際、成年被後見人の預金通帳・キャッシュカード・保険証券・実印・不動産の権利証等を預かる必要があります。
また、成年被後見人の親族がこれまで上記の物を管理してきた場合は、その者に事情を説明し、引渡しを求めることもあるでしょう。
- (3)預金通帳等の財産の占有を確保した後、成年後見人は、銀行や保険会社等に対して成年後見人就任の届出をします。第三者が成年被後見人の預金等を勝手に引き出さないようにする必要があるためです。
- (4)成年後見人は、今後の財産管理遂行のため、成年被後見人の財産を調査し、1ヶ月以内にその調査を終了し、その財産目録を作成し、裁判所に提出します。
- また、年間支出額の予定も裁判所に提出します。
2、財産管理事務
(1)後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する(民法859条)。
この条文が表わすように成年後見人は、被後見人の財産すべてに対する管理権限があり、財産管理事務をおこなう必要があります。
- (2)具体的な財産管理事務として、預貯金や現金・車や家等の資産の管理、介護施設や病院への費用の支払い、成年被後見人の年金の受け取り等日常的に行う事務があります。
加えて、成年被後見人の所有する不動産の売却、現状の生活が困難等の場合の介護施設への入所及び病院への入院契約、成年被後見人の所有する家の修繕の手配、相続財産の遺産分割協議、成年被後見の代わりに税務申告・訴訟を行うといった特別な場合に行う事務があります。
3、身上監護事務
- (1)成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない(民法858条)。
- このように、成年後見人は、被後見人に対する身上配慮義務が課せられています。
- (2)成年後見人の身上監護は、法律行為であり、事実行為ではありません。
- 具体的には、成年後見人の身上監護は、被後見人に代わって医療や福祉施設と契約をする等であり、被後見人の身体介護、家事を代わりに行う等は含まれません。
4、その他の事務
- (1)後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる(民法863条)。
- このため、成年後見人には、家庭裁判所に対する報告義務があるといえます。
- 実務上は、およそ年1回の報告となることが多いです。報告を裁判所の再三の催促があるにもかかわらず、怠ったりした場合には、家庭裁判所より成年後見人を解任されることもあります。
- (2)上記の報告義務として、被後見人が死亡した場合に、家庭裁判所に対する報告があります。
- また、被後見人が死亡すると、成年後見人の任務が終了することになるため、最終の収支報告を残存した財産の明細をまとめる必要があります。
- さらに、被後見人に相続人がいるときは、これらの者へ財産の引渡しを行う必要があるでしょう。
- (3)被後見の死亡により成年後見が終了した場合には、成年後見終了の登記を行います。
成年後見人の選び方
法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。
ただし、家庭裁判所の調査官が調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていてもその人が選任されないこともあります。
候補が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、選任します。
また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって考えが異なります。
過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようです。
理想的なのは、
-
○お金に関して絶対の信頼をおける方
-
○面倒見の良い方
-
○近所で生活している方
-
○本人より若い方
です。
最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあります。
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いです。
また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。
任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
-
1)未成年者
-
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
-
3)破産者
-
4)行方の知れない者
-
5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
-
6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば司法書士の方がより適切な管理ができます。
注意をしなければならないのは、後見人にも将来何があるか分からないことです。
後見人の業務の継続性を考えると信頼できる法人を後見人にする「法人後見」という方法もあります。
現在法人後見をしている機関としては、日本司法書士連合会が設立した(公社)成年後見センター・リーガルサポートがあります。